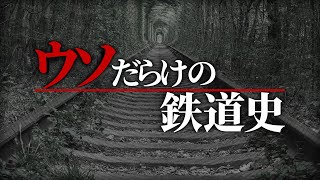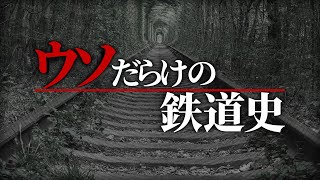
前回のおさらい:鉄道忌避伝説とは
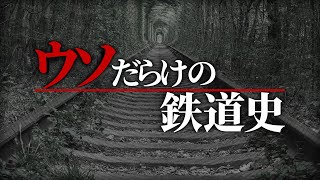
鉄道は意外と行けない場所が多い
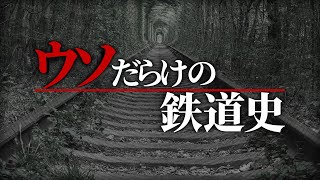
ということは、神戸電鉄はいったいどうなってるんだ!?
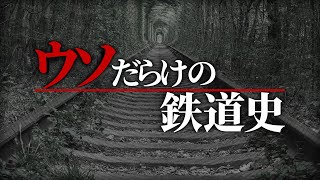
鉄道を敷いた頃の人からしてみたら、東京駅出てすぐの都会のど真ん中に30‰の峠ができた事は驚きに値するだろうな。
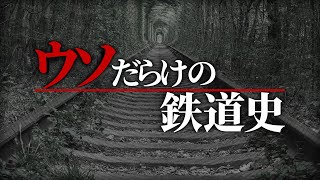
高輪ゲートウェイ駅は投票では新高輪駅だったんだけど、駅長の独断と偏見で高輪ゲートウェイ駅になったのです笑
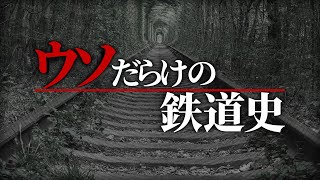
鉄橋とトンネルは作りたくない
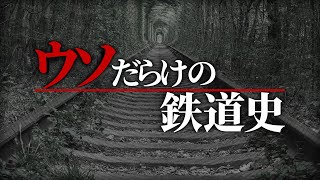
愛知県民(三河人)からすると、岡崎市の発音は「お→か→ざ→き」の平坦発音のイメージなので、岡本健作さんの発音(お↑か↓ざ→き→)が気になってしまった。
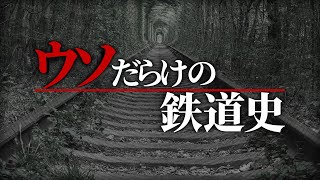
伝説に騙されていたオカケンさん
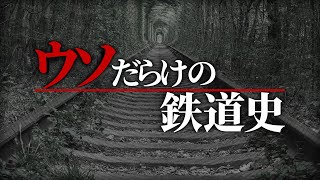
鉄道が学問になるまで
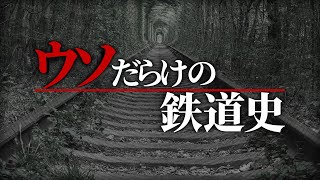
新聞無え 写真も無え俺らの村には電気が無え!
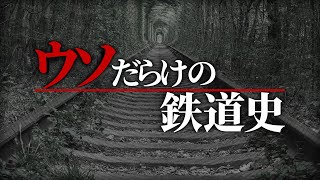
ここの「研究対象として見られなければ何も始まらない」ってのかなり示唆に富んでて面白いな…学問・研究の対象となるもの自体がかなり恣意性を持ってるっていう視点は忘れがち
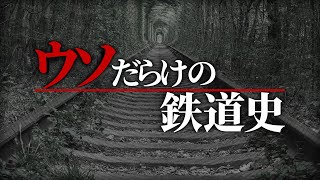
ジェンダー研究において、黒船以来、男の子は黒いもの硬いもの(産業革命以降、鉄製のものは強さ、成長の象徴)が好きっていう言われてみれば納得できる話がされてなかったのと、似てる気がする
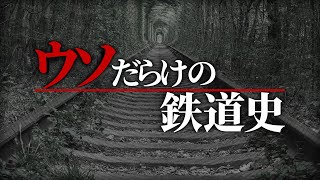
民俗学がお金にならなくなったという話で、国と会社から潤沢に資金が投下され、鉄道と民俗学と会社の一部門が密接にかかわっていた事例で満鉄調査部を思い出しました。鉄道の発明と発展により(と同時に?)帝国主義が拡大したように鉄道と軍事・植民地経営は非常に相性が良いので、ここからはまったくの想像になりますが、戦後教育の中で一部の鉄道忌避伝説が生まれたのも、当時の日本では戦前・戦中の鉄道のイメージが今よりもずっと軍事に近い感覚で、戦後の戦争忌避の感覚から、明治期の人々の気持ちを代弁した形で「なにか怖いものがくる」「生活に支障がでる」というふうになったのかなと思いました。岡本さんの話でもあるように自分が地元の鉄道忌避伝説を聞いたのも小学校のなにかの時間だったので、自分にも身に覚えがあり、腑に落ちます。ただ、しかし、鉄道は戦災・戦後復興の象徴でもあるので、上記の想像とは矛盾します…💦
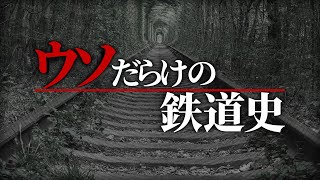
地方の鉄道会社のマイナー路線について資料探すとほぼ必ず町史に行き着くからガチで共感した。
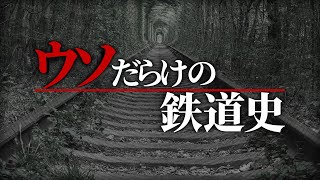
狭いあるある=良いあるある
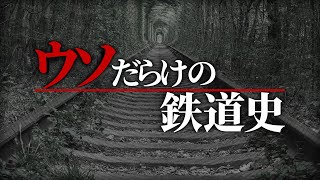
教科書が伝説を広めた?
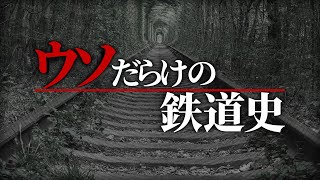
船橋京成船橋3分乗り換えチャレンジとかしたなぁ
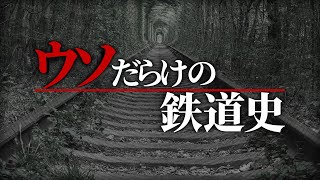
この縮尺は酷いw小学校の教科書見返して、この手の物があるか調べたくなった
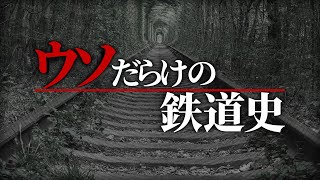
結論の背景 〜