動画数:130件

前回のおさらい:丙午とは?

すっごくどうでもいい補足なんですが、「甥が棺に横たわっている夢」というのは何かというと、フロイトが担当したある女性患者の夢の話で、彼女は「私の姉にはカールという息子がいるんですが、その子が棺に横たわっている夢を見ました。でも姉はカールの兄にあたる息子オットーを亡くしていて、私は『あの日』と同じようにカールがそこにいる夢を見たんです。私は姉に残された息子の〇までもを願っている、こんな私って最低ですよね」と訴えました。フロイトは「それは違うよ」と諭しながら話を聞いていったんですが、どうやらその女性患者は孤児で、幼い頃から姉(義姉?)の元で生活してたんですが、その家と関係のあった文学博士のような人物に恋焦がれており、彼の講演会があれば必ず出席する仲だったそうなんですが、結局(本人からも詳しくは語られなかった理由から)一緒にはなれず、最終的には疎遠になってしまったものの、オットーの葬儀の日に丁度その棺の前でその人に会うことができたのだそうです。フロイトはこの事例から「女性患者は無意識に同じことが起こることを望んでいる。つまり、夢は抑圧された欲望を表すものだ」と結論付けました

嫌われすぎて社会に害をなす俗信

学年同じままなの笑う

丙午の迷信はいつ現れた?

関ヶ原が6年前、家康が将軍になったのが3年前です。

犬将軍と技術革新で広まっていく迷信


原作改変がヒドすぎる丙午の物語

「歌祭文」は「うたざいもん」と読みます。些末なことながら失礼します。

丙午差別の始まりは魔女狩りと同じ

積読チャンネルみた僕「中世の魔女狩り・・・?」

俺が衝撃的だったのは、魔女狩りが広まった理由の一つもエロコンテンツだってこと別にエロコンテンツを悪く言いたいわけでは全くないが、魔女狩りや丙午差別が広まった理由があまりにも俗っぽ過ぎて、なんというか、小物たちのどうしようもなさってのを思い知った気分だ

間引きの川柳が詠まれる時代

激しく同意できますね。これと同じく「老害」もそうですね。3、40年後には「老害」という言葉はコンプラ違反になってると思っています。なぜなら現代多く使われている層である10~30代が還暦を迎えた頃に、ブーメランになり使えない言葉になるし、反論できる状態になる(ワイ70やけど、老害じゃない的な)。つまり「自分が言われたら嫌だ」という認識から、自ら無意識に忌避されると予想します。

「チー牛」ねぇ…あの言葉の何が悪いかがわからない人は1回起源をググってきてほしいどこまで行ってもタチの悪い悪口でしかないし、あんなのが広まる日本って世も末だと俺は思わざるを得ないあんたらはただ身勝手に彼らを蔑むだけだろうが、そんな彼らだって必死に生きていることには変わりないからな

何もかもが最悪な年、天明丙午。

爆笑した😂

〜 したあと寝ちゃうからかと思ったが可愛過ぎます😂😂😂😂笑笑めちゃくちゃ笑ってしまった

国のトップにも降りかかる迷信の火の粉

文明開化後の丙午はどうなった?
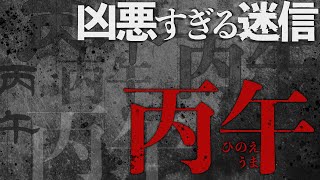
ちょっと変わったMBTI
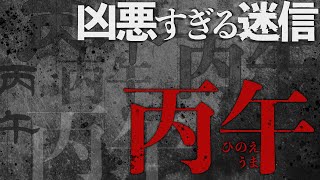
政府答弁書にも出てくる「丙午」とは?
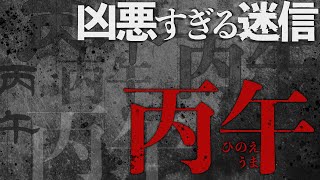
干支って60個あんねん
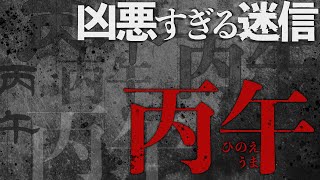
四柱推命の鑑定士の勉強と導入が一緒です😂
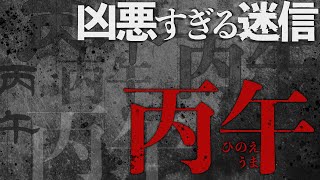
ロールパンナは陰陽思想の権化
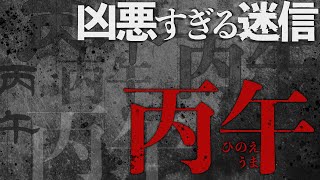
国会図書館のやつ引用してくれてる❗️
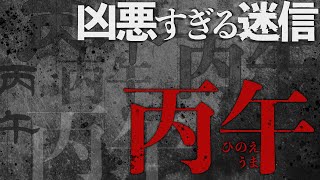
五行思想はくさ・ほのお・じめん・はがね・みず
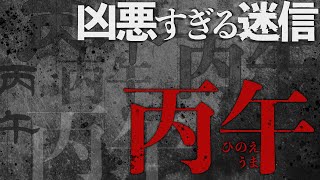
弱起の曲の方が少数派だよね
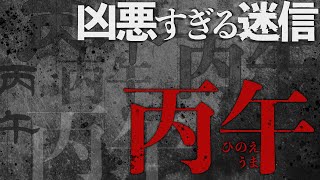
悲喜こもごもって言いますし、悲しいの方が先なのが日本語に組み込まれてそう?
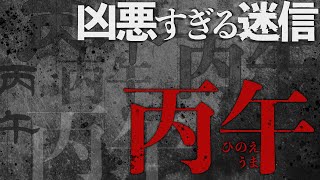
おっしゃる通りです。アジアでは陰陽の順番が多いと思います。軍歌の軍艦行進曲の歌詞も「守るも攻めるも黒鉄の〜」と始まります。仏教の教え七仏通戒偈も「悪いことをするな、良いことをしろ、なまけず真面目に生きろ」の順番です。アジアに近い宗教ほど「悪いことするな(ルールを守れ)」ヨーロッパに近いほど「いいことをしろ(ルールを破っても英雄的なことを!)」孔子も「己の欲せざる所は人に施す勿れ」ですもんね。興味深いですよね。
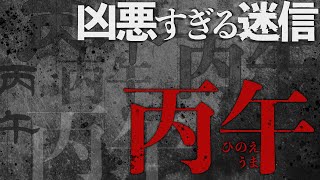
3の倍数でヒソカになる干支
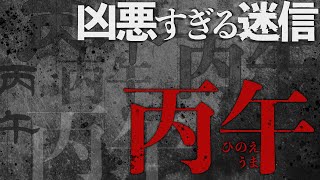
現代でも土は変わり目に現れて、土用の丑の日の土もその意味だったはず。無理矢理当てはめたと言われればそうかも知れませんが。
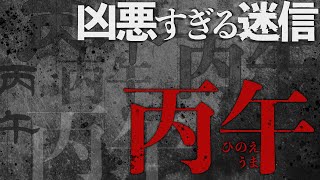
干と支がどちらも+1されるので、奇数同士偶数同士が組み合わさっていると考えています。異世界の干支にするなら、陰陽を逆にする必要がありそう。
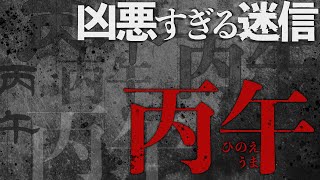
弱火でじっくりやっぱりHUNTER×HUNTERじゃないか!!!
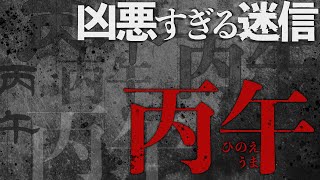
ホルビー?
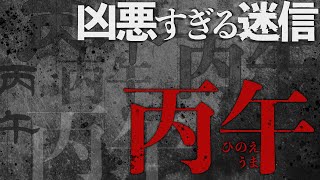
ゆる民俗学ラジオで差別を根絶したい
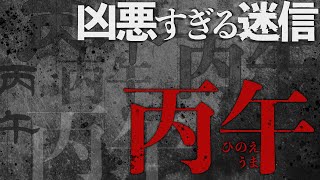
警察あたりの隠語で赤馬は放火の意味

ようやく始動した新企画

関東では見ない石像がなぜ池袋に

いつの間にか参拝されている像

ゆるナイトスクープラジオ

若いうちから盆栽を始めよう

ゲーム実況第2弾は『ウツロマユ』?

NHKのオタク量産アニメ『クラシカロイド』

ゆる民俗学ラジオと日本酒がコラボ!
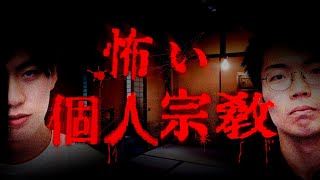
個人宗教ちょっと怖いやつ編
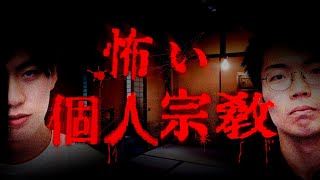
行きと帰りは同じ道でないと呪いになる
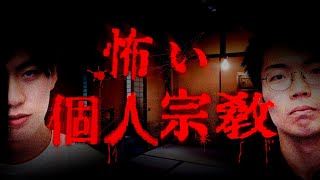
バイクで林道走る人間ですが、木が倒れて通れなさそうだったら大体はそこで引き返します。引き返す理由としては「人の意志で倒木を設置されていることが多く、その先に進んでほしくないから」です。
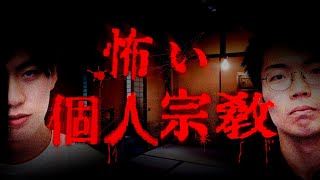
本当に耐えられないトイレは可、めちゃわかる笑
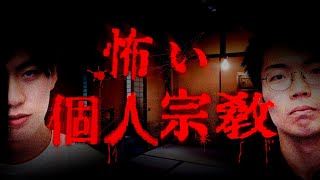
怪異と対峙するものは片目で描かれる
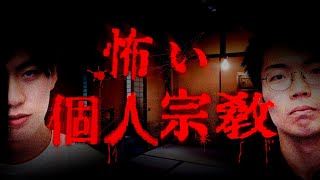
西洋医学的にも頸部にはリンパ節がたくさんあるので、病気(特に感染症)などのよくないものがあると首が痛みます。両方の面からそこを守ろうとする習俗ができるのは理解できます。
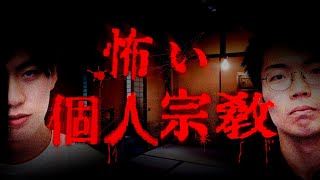
失敗した絵や文字は化けて出てくる
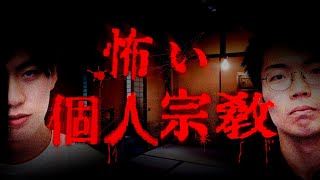
片目というと片目片足の妖怪一本だたらを思い出します。
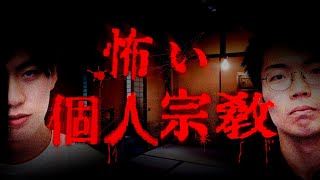
千本丸太町バス停の隣のバス停使ってるから民俗学好きな人が近くに住んでるんやって勝手に嬉しくなりましたw
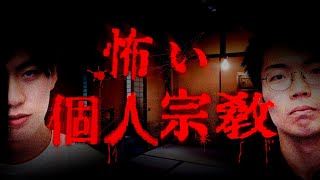
ハンコとかビジネスマナーと民俗学について話してほしいです
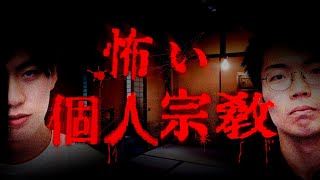
私はpcなどで長めの文章を書くときは、書き直すために削除する部分は巻末に「削除用のセクション」を作ってそこに移動してます。PDFなどに出力をするときはそこは含まないようタグをつけて設定しています。別のところで使うかもとか、削除したことを忘れて書いてある前提で進めてしまう恐れがあるからとか、理由は色々あります。しかしこれ、文中に削除部を残して、削除用のタグをつけることもできるんですよね。わざわざなんとなく手間をかけて移動していたことを自覚してなかったんですが、この動画を見てふと気づきました。
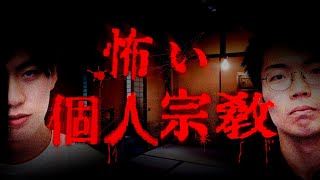
サイエンスの界隈では、実験ノート(記録などを書き記すもの)にはボールペンを使え、消すなと言われますねこれはたしか実験記録の捏造や偽造などを防ぐ目的があったと思います
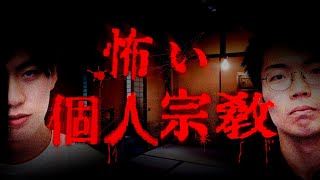
わたしも算数の家庭教師の方に、間違えた途中式は消さないようにボールペンで全て書くように言われました…!
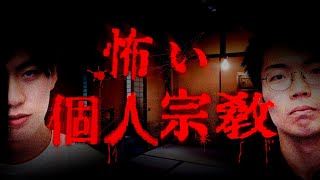
妖怪が見えてしまうバグは整頓でデバッグ
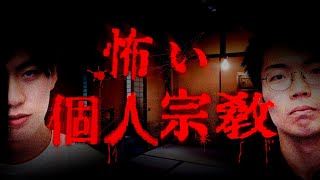
「うちの部屋の幽霊」って面白い

民俗大辞典とのエキゾチックな出会い

エイプリルフールの始まりはいつ?

怪談かと思ったら歴史の話だった

一瞬「デマンドバス」が民俗学辞典に載ってるのか…!?、と思って焦ってしまった…

ライドシェアが出てきて業態も変わりつつあるね

田舎の方が外国人花嫁は多い

この部分の話を聞いてたら(特に韓中に対して)旧統一教会の合同結婚式がちらついてしまった・・・すいません・・・要らないコメントして・・・

この頃の農家がフィリピン人の妻を買ってきたって話相当有名だと思ってたんだけど逆にときひろさん達みたいなインテリ層でも知らないのかとびっくりしてしまった

俗信が医学的に正しいと証明された例

欧米人の 9割は湿性の耳垢なので乾式の耳垢があることを知らない人が多い

実家は訛ってたのか「ヤネ耳」じゃなく「ヤニ耳」と呼んでましたね。カサカサしてるのは「コナ(粉?)耳」と呼んでました👂

耳の中に水が入ってなかなか出てこない時は、「もう一度耳の中に水を入れてすぐ耳を下に向ける」とスルッと流れてきます。

水が入った耳側に頭を傾け、同じ側のコメカミを軽く叩きつつ、同じ側の足でケンケンする私はコレでてきめんに取れる

「耳かき気持ちいい」という言説はフィクションだと思い、耳かきASMRが商品として成り立つことの意味が分かってなかった私ですが、そういう人がいるんですね……(耳かきが痛くてたまらなくて大嫌いな人間)

パチンコへの思い入れが強い筆者

漫画『釘師サブやん』を思い出した…

黒川さん「パチンコを作ってみようみたいな、図工の授業があって」僕「ピンボールって言えよ」

現在、台で喫煙できる店はないんじゃないかと😅2020年前後の東京オリンピック(受動喫煙がどーたら問題)で一気に喫煙ブースや店外に追い出されたように記憶してます

うちの近くのはゲーセンになってたなあ

パチンコ屋といわゆる「暴力団」の癒着(というか系列化?)ってよく問題視されるような…あれは解消したんだろうか?

キムチと和食の裏には同じ思惑が

キンパプの具なんかの風味に「唐辛子以前のキムチの味」が残ってるのかも?

5選なのに9冊な2024年のベスト本

演出の芯を教えてくれる本

Y字路の多い横浜の民、必読の書。

民俗学はインターネットも扱える

虚構推理の鋼人七瀬のエピソードが浮かんだ。

その流れ自体を題材にした作品として「つねにすでに」があったりして面白い。作者は本当にインターネットが大好きすぎる。

今が読みどき、思わず車を買ってしまうマンガ。

乱と灰色の世界よみなおしたいなぁ!

超骨太な民族学雑誌

ノンフィクションとは思えないほどドラマチック

喋っても喋り尽くせない『増殖するシャーマン』

もうなんかそういうのじゃない

「七宝を順繰りに体に取り込んでいく」だからラピスラズリだったのか。いわれるまで考えもしなかった。あのくだりは三族との対応関係にうまく収まらない異物感があったのだけれど、七宝を意識したアイテム選定だったのだと考えると一定の納得感がある、かも。

「元気な人だけ読んだらいいかな」その注意は本当に大事です!

ここの「見んなって! 最後のページ!」が好きすぎて何度も見ちゃう。

特訓後の日本民俗語彙クイズ

SNSでよくバズるタコ

北斗晶さんは本名ひさこさんですね、プロレスラー特有の滑舌でチャコちゃんになったと思われます。健介の師匠は長州ですから。

「ねこ」は、「ねぇねぇと鳴く仔」からだと聞いた事があります。「猫」って漢字の「苗」部分も、「(中国語で)びょうびょうと鳴く」ところからだと聞いて、「同じだ」と思った記憶があるので、覚えていました。

イキリ具合で占える

沖縄では、つむじの数で性格が分かると言われています。「ターチマチュー(2つのつむじ)は、ウーマクー(わんぱく)」だとか。信憑性は定かではありませんが、つむじが1つの人に比べると髪のセットが大変そうなので、それがわんぱくっぽく見えるのかもなぁーと勝手に思ってます。

民俗語彙早押しクイズ

語り部のび太「まず宇宙が誕生してね。」(あやとりで「ギャラクシー」を作りながら)

大塚英志さん原作漫画の『木島日記』に似たような描写が出てきましたね…あちらでは、薪程度の木の棒にバーコードのような刻みが入っていて、白痴(物語当時の語彙)の子どもがその表面をなぞって読み取り、記憶から対応する物語を朗々と語り出す、という現代に寄せた脚色が入っていました。最近黒川さんが記憶装置の木の棒の話をする度に「黒川さん『木島日記』の話しないかな…読んでほしいな…」とうずうずしてしまうのでここに記念マキコ

世界中でやられているイッポンカエカエ

各地に色々な言い方があるオチャメンコ

民俗学者は知っているツクマイムシ

秩父市皆野町ではなく秩父郡皆野町ではないでしょうか
